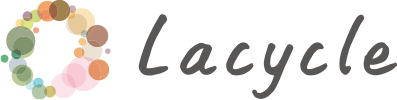プロローグ 曲がりくねった山道をのぼった先にある、3軒の民家が残る小さな集落へ。目線の高さほどに山の稜線が広がるここは徳島県つるぎ町の三木枋(みきとち…
プロローグ
曲がりくねった山道をのぼった先にある、3軒の民家が残る小さな集落へ。目線の高さほどに山の稜線が広がるここは徳島県つるぎ町の三木枋(みきとち)集落。2018年に「世界農業遺産」に選ばれた「にし阿波」エリアにあります。
この地で400年以上に渡り代々農業を営んできた磯貝家は、現在、16代目の勝幸さんとハマ子さんご夫婦、そして犬のコロスケとアンコの二人と二匹暮らし。ふもとの町で暮らす息子の一幸さんも毎日山にあがってきて、一緒に農作業を行っています。ソバや雑穀など「にし阿波」ならではの食物のほか、「スーパーマーケットで売っている野菜はほとんど自分の畑でまかなえる」というほど多品目の野菜を育て、味噌やこんにゃくなどを手づくりしながら暮らしています。また、そんな自給自足的な山の暮らしを体験できる農家民宿「そらの宿 磯貝」も営んでいます。
本連載では、この土地で脈々と受け継がれてきた生活を営む磯貝家の春夏秋冬をお届けします。


【第3回 最終回】厳しい冬を越えて春の息吹き、ふたたび(前編)
山暮らしの美味しい保存食
気温がぐんと下がりはじめた12月、干し大根づくりがはじまると聞きつけて磯貝家へ。
到着するとちょうど一幸さんが荷台いっぱいに載せた大根を畑から運び出しているところでした。「今季の大根は今日で全部収穫し終わった」と一幸さん。畑を見ると、土の上にびっしりと横たわる大根の葉。このままカヤ(*屋根材や肥料等に利用されてきた植物)を混ぜて耕して自然の有機肥料をつくります。
冬がはじまる前から、もう次の春に向けた畑づくりがはじまっていました。

標高400メートルを超える三木栃地区。ふもとの町よりもさらに気温が下がっているように感じます。
「最近はめったにないですが、ここは毎年たくさんの雪が降って、春が来るまで畑の隅に雪がずっと残っているような地域。子どもの頃は30センチ以上も雪が積もることもありました」と一幸さんが教えてくれました。
そんな山の厳しい冬を乗り越えるため、昔からこの地では干し大根や干し芋などの保存食がつくられてきました。

お茶休憩が終わり、「さあ、そろそろやるで」とハマ子さんは納屋の軒下に腰を下ろすと、大根の皮を一本一本むきはじめます。

「これはシュロの葉でつくった紐。前もって葉を割いてこういう紐をつくっておくんよ」
皮をむいた大根の先にキリで穴を開け、そこへ紐を通していきます。もちろんこのシュロの葉もここで育ったもの。


「『ねじ干し』にはシュロの葉。『刺し干し』っていう干し方は、もち米の稲藁(わら)を輪切りにした大根の真ん中に通したあとそのまま湯通しから干すんよ」
大根1本を吊るす強度を持ったシュロの葉、茹で加工にも使いやすいもち米の稲藁と、「ここにあるもの」を使いながら、干し方によって使い分けているそうです。

「今は大根が曲がっとるけど、吊るしていると水分が抜けてだんだんまっすぐになっていっていくんよ。それからもっと水分が抜けると布を絞ったみたいにねじれてくるけん、『ねじ干し』って言うんよ」
一本をまるごと吊るす干し方は「丸干し」ともいいますが、ここでは「ねじ干し」と呼ばれています。
風通しの良い日陰に吊り下げて2週間ほど干したあと、さらに屋内で陰干し。ほどよくしんなりしているうちに輪切りにして、さらに天日干し。しっかり乾燥させれば、「ハリハリ」と呼ばれ親しまれている干し大根の完成です。

「次の日には、農業体験の学生たちが磯貝家にやってきて、一緒に干し芋づくりをするんよ。そのあとは年末まで年越し蕎麦づくり。今年はたくさん注文が入っとるけんな、忙しいわ」
年越しソバづくりはハマ子さんの毎年最後の大仕事です。
山の上に芽吹く春
厳しい積雪も重なって、年が明けて磯貝家へ向かうことができたのは、雪がすっかり溶けて春の芽吹きを感じはじめた頃でした。

「これだけ積雪の多い冬は久しぶり」と一幸さん。ふもとの町で暮らす一幸さんが三木栃地区まで登って来られない日が何日もあったと話します。春を迎える準備も少し遅れているようで、猿避けの対策をしたり、タラの芽を育てるためのハウスを建てたりと、黙々と畑仕事を進めています。

「天ぷらにして自分らで食べようと思って一昨日採っておいたんよ」と、ハマ子さんは袋いっぱいに入った食べごろのフキノトウを見せてくれました。
「そこの栗の木の下あたりにフキノトウがあるき、探してみ」
ハマ子さんに言われて、急な斜面を恐る恐る下っていくと、フキノトウを発見! しかし、花が咲いてだいぶ大きくなったものでした。

もともと自生していたフキノトウに加え、町をあげてフキノトウの栽培を試みた時期があったそうで、そのときに植えたフキノトウの品種「みさと」がこの場所に根付いているそうです。

干し大根がたくさん吊るされていた小屋を覗くと、12月頃に収穫したという唐辛子と、塩茹でしたそば米が、ひんやりとした風を受けながら干されていました。

「干し大根もきれいに仕上がったよ」と、出てきたのは3種の干し大根。
「ハリハリ」、「千切り」、「刺し干し(厚切りや湯通しとも呼ぶ)」と呼ばれるこれらは、磯貝家でよくつくられているラインナップ。一度湯通ししてから干す「刺し干し」は、手間の分だけ旨味が強く、お煮しめやおでん用にぴったりだと教えてくれました。

ハマ子さんがつくったハリハリ漬けをいただきました。くねくねした食感と柔らかい歯ごたえがクセになるうえに、大根の旨味が凝縮していて、ごはんが何杯も進みます。
「明日は干し大根と一緒に、このハリハリ漬けも一緒に店に出せたらと思っていっぱいつくったんよ」
夏季(6月〜10月)を除くほとんどの週末、ハマ子さんは家から車で約15分ほど山を降りたところにある「剣山木綿麻(つるぎさんゆうま)温泉」へ向かいます。入り口横にある小さな小屋が磯貝農園の「店」。旬の農作物や手づくりの加工品を販売しているのです。
※他マルシェへの出店や諸事情などで出店しない日もあります。
後編では、剣山木綿麻温泉の開館時から25年以上続けてきた出店の準備の様子をご紹介します。

磯貝農園(そらの宿 磯貝)
tel.090-9555-7806/0883-62-4075
徳島県美馬郡つるぎ町貞光字三木枋109
https://www.instagram.com/isogainouen/
※ 宿泊利用者は磯貝家の農作業や手仕事の体験ができますが、季節によって体験できる内容が異なります。詳細はお問い合わせください。(そらの宿 磯貝について https://nishi-awa.jp/stay/1170/)
今回取材した磯貝農園は、Lacycle mallで出店しています。

磯貝農園は2018年に「世界農業遺産認定地域」に選ばれた「徳島県にし阿波地域」、徳島県つるぎ町の三木枋(みきとち)集落にあります。この地で400年以上農業を営んできました。ソバや雑穀など「にし阿波」ならではの食物のほか、多品目の野菜を育て、味噌やこんにゃくなどを手づくりしながら暮らしています。