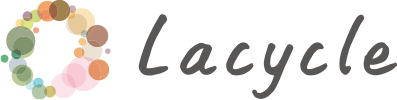プロローグ 曲がりくねった山道をのぼった先にある、3軒の民家が残る小さな集落へ。目線の高さほどに山の稜線が広がるここは徳島県つるぎ町の三木枋(みきとち…
プロローグ
曲がりくねった山道をのぼった先にある、3軒の民家が残る小さな集落へ。目線の高さほどに山の稜線が広がるここは徳島県つるぎ町の三木枋(みきとち)集落。2018年に「世界農業遺産」に選ばれた「にし阿波」エリアにあります。
この地で400年以上に渡り代々農業を営んできた磯貝家は、現在、16代目の勝幸さんとハマ子さんご夫婦、そして犬のコロスケとアンコの二人と二匹暮らし。ふもとの町で暮らす息子の一幸さんも毎日山にあがってきて、一緒に農作業を行っています。ソバや雑穀など「にし阿波」ならではの食物のほか、「スーパーマーケットで売っている野菜はほとんど自分の畑でまかなえる」というほど多品目の野菜を育て、味噌やこんにゃくなどを手づくりしながら暮らしています。また、そんな自給自足的な山の暮らしを体験できる農家民宿「そらの宿 磯貝」も営んでいます。
本連載では、この土地で脈々と受け継がれてきた生活を営む磯貝家の春夏秋冬をお届けします。


【第3回 最終回】「ここにあるもの」でつくり、繋ぐ(後編)
自家製100パーセントの手づくりこんにゃく
つるぎ町の日帰り温泉「剣山木綿麻(つるぎさんゆうま)温泉 」での出店前日のこの日は、販売用のこんにゃくづくりの日。

秋に収穫したこんにゃく芋と、在来種で育てているソバの藁(わら)でつくった自家製の灰汁(あく)のみを使用した100パーセント手づくりのこんにゃくです。保存料が一切入っていないため、賞味期限は一週間程度。出来立てを食べてもらえるようにと製造はできるだけ出店の前日に行います。

アクが強く手荒れしやすいと聞いたことがありますが、「慣れとるけん平気」と素手で皮をむくハマ子さん。「皮が残っとると商品にならんけんな。きれいにむかんとな」と念入りに作業を進めます。

皮をむいたこんにゃく芋をかまどで茹でたあと、ミキサーにかけてとろとろに。そこへ、ほんの少しずつ水を入れながらダマが無くなるまでしっかり混ぜます。
10分以上は混ぜたでしょうか。最後に自家製の灰汁を加えて、再びしっかり練ると生地の出来上がりです。
「灰汁を入れたらすぐ固まってしまうけん、それまでに柔らかくなめらかな生地をつくっておくんが大事なんよ」とハマ子さん。「灰汁を加える量は“ええ加減”よ(笑)」と、長年の感覚で測っている様子でした。

生地が仕上がったら、大きめにひと掴み。ぎゅっと握ってしばらくころころしていると思えば、ハマ子さんの手の中であっという間にまんまるいこんにゃく玉ができていました。

「こんにゃくはここでは正月の食べもん。うちでは昔から正月に雑煮や一般的なおせち料理のようなもんはないんよ。一年の砂を落とす『砂おろし』って言うてな。こんにゃくを刻んで白和えにして食べるんよ」

木ベラで叩いてポンポンと弾むような音が出れば茹で上がりの合図。
しっかり冷ましてから翌朝の出店前に袋詰めをします。

「ちょっと味見してみ」と言われ、出来立てを刺身こんにゃくでいただきました。
とにかくなめらかな歯触りで、クセがなく、つるんと食べられるこんにゃく。生まれて初めて本当のこんにゃくを食べたような感覚でした。
(※磯貝農園では、事前予約をすればこんにゃくづくり体験が可能です)
25年以上、週末の慌ただしい朝
出店日の朝、かまどの湯が沸いて湯気がもくもくと立ち込めています。

この日の出店準備は団子づくり(第2回参照)から。しばらくして、一幸さんもふもとの町から上がってきて、出店用の餅をカットしたり、賞味期限シールを貼ったりと、ハマ子さんを手伝います。

続いて、自家製のソバ粉と小麦粉でつくる二八蕎麦。畑で採れた山芋をほんの少しすりおろして入れるのがポイントだそうです。
何百年と受け継がれてきた在来種のソバからできる手づくり蕎麦は香りが強く、一口いただくと蕎麦の風味が驚くほど口いっぱいに広がります。

「祖谷(いや)の生まれやけんな、昔から母がつくってたんは覚えとる」

昼前頃にはようやく商品が揃い、大きな白菜もいくつか一緒に車に載せると、剣山木綿麻温泉へ。いよいよ磯貝農園のお店が開店です。
「あれこれ考えるんが楽しいんよ」
剣山木綿麻温泉に出店しはじめて25年以上。徳島県最高峰の山、剣山の登山口に向かう道からほど近くにある剣山木綿麻温泉は、登山客を中心に県内外からお客さんが訪れます。ここで磯貝農園の農産物やハマ子さんの手づくりの加工品に出合ったことをきっかけに、毎年のように注文をくれるお客さんもいるそうです。

車の免許を持っていないハマ子さんは、夫の勝幸さんや息子の一幸さんの運転でいつも商品を運んでもらっています。最近では、義嫁の理恵さんも手伝ってくれるようになりました。
「昔は女性が車の免許なんか取るもんでないって言われていたんよ」と話してくれました。そんな時代を乗り越えて、ハマ子さんが「何かをしたい」と動きはじめたのは、3人の子育てを終えたおよそ30年前の50歳頃のことだといいます。ちょうど、道の駅貞光ゆうゆう館や剣山木綿麻温泉の開館が続き、町の特産物づくりが活発になってきた頃でした。
畑ですくすく育っている栗を使って団子をつくって売ってみよう、ソバを育てているんだからとソバ打ちをしてみよう、と湧き出るアイデアを試しはじめたそうです。多品目少量栽培で農業を営むだけでなく、麺製造業や菓子製造業も取得して、「ここにあるもの」を商品にし続けてきました。

「今日は試しに団子に佃煮を入れてみたんよ。中華まんみたいになるかなと思ってな。試食してもらおうと思って」と、新商品を持ってきたハマ子さん。「あれこれ考えるんが楽しいんよ」とまだまだアイデアが止まらない様子です。
この味を、この文化を、継ぐこと
「理恵さん(義嫁)も店に立ってお客さんに顔を覚えてもらわなと思っとるんよ。こんにゃくももうだいぶつくれるようになってきたんでよ。きなこ飴はもうほとんど一人でできるし」とハマ子さん。

「まだまだ全然」と理恵さんは苦笑いです。「きなこ飴をつくるためにはったい粉を計って配合することができても、はったい粉自体はまだお義母さんにつくってもらわないとできないんですよ。はったい粉は苦さが出ない程よい香ばしさになるように炒る、その具合が難しいんです。まずは、きなこ飴を材料からひととおり自分で揃えられるようになることが今の目標です」

「お義母さんのつくるものの美味しさを知っているから、自分には同じものはつくれないという不安がある」と話す理恵さん。「自分はおやじのやっとったようにはできないと諦めてるよ」と笑う一幸さん。磯貝農園を継ぐと決めて農業をはじめたのは2020年のことです。
「実際に足を踏み入れてみて、いかに両親がやってきたことがすごかったか身に染みました。いつかはその域に少しでも近づくことができるかもしれないけれど、まったく同じにはなれないと思ってます。でも、自分にしかできないこともあると思うし、たとえ真似事でも、ここの農業や食文化を残そうとすることは大事だと思ってやっています」
ここにしかない景色と、ここで生まれた味を、私たちがただ体験することも、その架け橋の一部になれるかもしれません。

もうすぐ春。
母屋の裏の畑で、また今年もじゃがいもの種植えがはじまります。
「春になったらゼンマイやワラビを採りにいかなあかんし、タケノコを掘ってきて湯がいたり、雑穀も植えなあかん。そのあとはこんにゃく芋の種植えやなあ」とハマ子さん。
山の上に暮らす磯貝家にまた季節が巡ります。

磯貝農園(そらの宿 磯貝)
tel.090-9555-7806/0883-62-4075
徳島県美馬郡つるぎ町貞光字三木枋109
https://www.instagram.com/isogainouen/
※ 宿泊利用者は磯貝家の農作業や手仕事の体験ができますが、季節によって体験できる内容が異なります。詳細はお問い合わせください。(そらの宿 磯貝について https://nishi-awa.jp/stay/1170/)

磯貝農園の商品は、Lacycle mallでお買い求めになれます。
「世界農業遺産」のにし阿波、徳島県つるぎ町の三木枋(みきとち)集落で、昔ながらの製法で作られた、プルプル食感のおばあちゃんの手造りこんにゃくです。
【5月までの販売となります。】